
◇簡易gm測定器◇

gm測定器の原理
| 真空管の増幅率は負荷抵抗の値に比例する性質があります。このときの比例定数を相互コンダクタンスといい「gm」という記号で表します。
また、この「gm」が大きい球ほど高い増幅率になります。そしてgmを求めるのには、プレート電流の変化を第一グリッド電圧の変化で除算した値となります。 |
◇バラックで実験◇

以前制作した簡易型真空管試験機から給電です。
| 例として、第1グリッド電圧が−1Vの時、プレート電流が2mAとします。
第1グリッド電圧が−2Vの時、プレート電流が1mAなら2mA−1mA/1V−1mA/1V=1m℧(mho)となります。 このことから第1グリッド電圧を1V変化させプレート電流の減少値(mA)を読み取りgmを求めます。 簡単に作るためプレート、第1グリッド電圧は100Vにしました。規格表に100Vの動作例が無い球は、換算図から計算で求められます。この方法は私のHP「球つれづれの2 電圧を変えた場合の出力管の動作例の計算」にあります。この例ではgmの計算がありませんが、図のFgmを使って下さい。(付属のデータはEp.Esg=100Vのデータです。) 例えば6AR5のgmが1500と書いてありますが、これはEp.Esg=100Vのデータです。この球をEp.Esg=250Vで使えばgm=2300になります。 |
◇Tube data◇

| 【構 造】
安価に作るためにトランスレスとしました。感電防止法は配線図を見て下さい。また、100V:100Vのトランスをお持ちでしたらそれを利用されても良いでしょう。 電圧計(最大-20V)と電流計は外付けとします。電流計はオートレンジのテスターが便利です。 ソケットとヒーター電源は私のHPにある「簡易型真空管試験機」を使いました、100Vの安定化電源のTRはTVの解体品を利用しました。 球の電極接続は蓑虫クリップ利用です、第一グリッド用だけはグリッドキャップの球があるので大型のものを使いました。 直熱管はフィラメントにハムバランサーを入れその中点をカソードにするのが正式ですが、フィラメントの片側につなぎました。 ヒーター電源を巻いて、いろいろな球を測ってみようという方は私のHPのHP「簡易型真空管試験機」を見て下さい。しかし6.3Vのだけでも、かなりの球を測定できます。 周波数変換球は変換コンダクタンスなどは測れないので、3結にしてそのGmを求めます。 高Gmの球はパラスチック発振を起こしやすいので、ソケット近くの配線にフェライトビーズを入れると良いでしょう。 |
◇試作した回路図◇
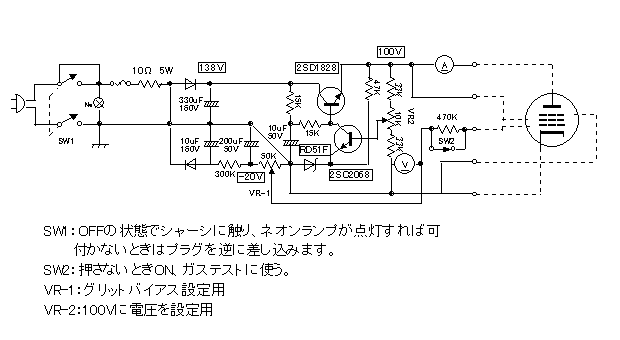
| 【測 定】
球に規定のバイアス電圧を加えます。プレート電流を読み、ガステストのスイッチを押します。そしてプレート電流が変化しなければ合格です。 プレート電流が増える球はガス電流が流れており、抵抗結合の出力管では第一グリッドに+の電圧が出ます。同様に中間周波増幅管ではAVC回路が+になります。 合格ならプレート電流(P11)をよみ電卓に入れます。 次にバイアス電圧を1V増やします。そして読み取ったプレート電流(P2 )からP1-P2=(mA)の値を求め1mAなら1m-mhoになります。高Gm,グリッドバイアスが浅い球は、グリッドバイアスの変化を0.5Vとしてプレート電流の読みを2倍にします。 【判 定】
|
|
TV−2との比較表 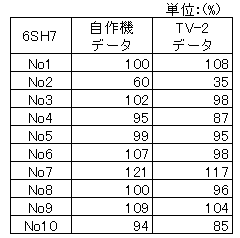
| 今回はこのような簡易gm計を作ってみましたが意外と良い結果が出ました。
そして球のデータに乗っていない球も規格表から簡単に計算出来ます。また、定電圧電源を250V、100Vに設定すれば規格表に乗っているgmが読めます。 試しに、この試験機で測った値がどの程度正確なのか%のデータが測れるTV−2の試験機で調べてみました。
|
<2010.03.20>